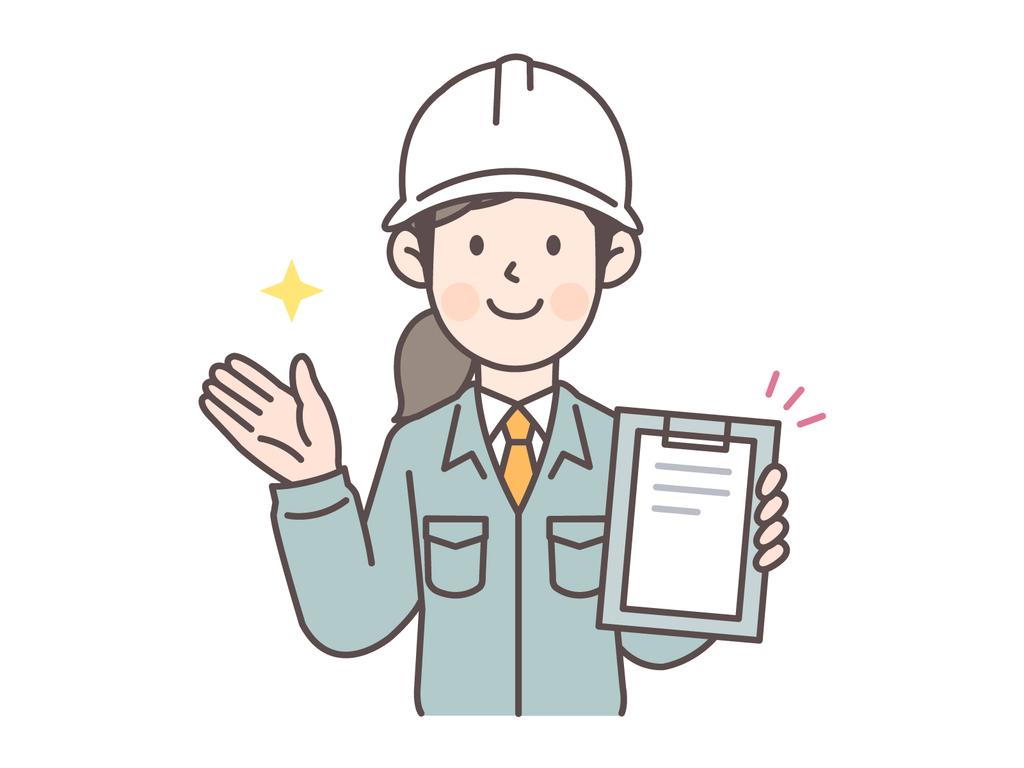個人事業主と一人親方の違いとは?労災特別加入で安心な働き方
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
個人事業主と一人親方の基本的な違い
個人事業主とは?その定義と特徴
個人事業主とは、法人を設立せずに自分一人で事業を営む人を指します。
税務署に開業届を提出し、個人として事業を行う形態で、多くの場合、IT業、飲食業、小売業、デザイン業など様々な業界で活動しています。
個人事業主は、事業の自由度が高く、自分の裁量で仕事を進めることが可能である一方、事業主としての全ての責任を負います。
そのため、収入の安定や福利厚生の確保は自分自身で行う必要があります。
一人親方とは?その定義と働き方の特徴
一人親方とは、自らも作業を行う個人で、建設業や林業など特定の業種に従事する人を指し、一般的に従業員を雇用せずに仕事を請け負う形態です。
例えば、大工、配管工、電気工事士などの職種が該当し、必要に応じて施主や請負会社から仕事を依頼されます。
一人親方は、通常、法人や雇用契約の枠を持たないため、労災保険の特別加入制度を利用して自身の安全が守られる仕組みを選択するケースがあります。
この制度を利用することで、万が一の労災事故に対する保障を確保することも可能です。
一人親方と個人事業主の違いを整理!
一人親方と個人事業主は、どちらも従業員を束ねる立場でない自営業者に分類されますが、大きな違いがあります。
主な違いの一つは業種の範囲です。
一人親方は建設業や林業など特定の業種に限定されますが、個人事業主は飲食業やIT業など幅広い業界で活躍できます。
また、一人親方は原則として従業員を雇用せず、必要に応じて年間100日未満の期間的な雇用が許されるのに対して、個人事業主にはこうした制約がありません。
さらに、一人親方は労災特別加入制度により一人親方団体を通して労災保険に加入できるのに対し、個人事業主は基本的に労災保険の対象外、ただし、労働保険事務組合を通して中小事業主の労災保険に特別加入する必要があります。
一人親方のメリットとリスク
一人親方になることで得られる自由と柔軟性
一人親方として働く最大のメリットは、自由度の高さと柔軟な働き方が可能である点です。雇用契約ではなく請負契約に基づくため、自らが仕事の内容や取引先、スケジュールを調整できます。
特定の企業や雇用主に縛られることなく、自分のペースで働けるのは大きな魅力です。
また、個別に契約を行うことで、自身の能力を最大限発揮できる環境を選ぶことが可能です。
さらに、成果に応じた収入が得られるため、高いスキルを持つ人にとって収入の向上も期待できます。
労働者ではないことによる保障の欠如
一方で、一人親方である以上、労働者としての法的保護が適用されない点には注意が必要です。
通常の雇用契約に基づく労働者が受けられる労働条件や社会保険制度に基づく保障は存在しません。
そのため、失業給付や健康保険、厚生年金といった一般的な社会保障制度の恩恵を十分に受けられず、自分自身で備えておく必要があります。
特に、労働災害に遭遇した場合には、自らが治療費や生活費を負担することになる可能性があり、リスク管理が求められます。
仕事の継続性に伴う責任やリスク
一人親方は、自分自身が事業主であり、仕事の受注から実際の作業、管理業務まで全てを一手に引き受ける必要があります。
このため、仕事が途切れないように安定的に受注を確保する責任は常に自身にあります。
取引先の都合や市場環境の変化により、収入が不安定になる可能性もあります。
また、事業の収支管理や請求関連の書類作成など、経営に関する業務負担も重くなります。
こうしたリスクへの対応力が求められる点は、雇用労働者とは異なる特徴です。
請負契約の特性がもたらす課題
一人親方として働く場合、請負契約が中心となります。
この契約形態では、業務委託を受けた仕事を完成させる責任が生じる一方で、作業プロセスにおける管理や指導を受けることが基本的にはありません。
このため、業務遂行に必要な知識やスキルを独自に習得しなければならないほか、想定外の事態に対処する能力も必要です。
また、契約先からの支払い条件や契約内容の変更に伴う金銭的リスクが伴うこともあります。
これらの課題に対する準備や対策を講じることが重要です。
特別加入で安心を確保する方法
労災特別加入制度とは?その概要
労災特別加入制度は、通常の労災保険では対象外とされる自営業者や一人親方の方々に限定的に加入を認める制度です。
この制度では、業務中の災害や通勤中の事故などに対して、治療費や休業補償、遺族補償などが提供されるため、個人事業主も労働者に近い形で保険の恩恵を受けられます。
一人親方とは?と言われる場合、特にこの制度を利用することで安心した働き方を確保できる点が特徴です。
一人親方が特別加入できる業種
一人親方として特別加入できる業種は、主に建設業や林業、漁業などの身体を使った作業が多い分野に限定されています。
具体的な職種としては、大工、左官、電気工事士、塗装工、配管工、鉄筋工事業者、内装工事業者、解体工事業者、造園業などが挙げられます。
このような業種で働く個人事業主は、労災特別加入の対象となることが可能です。
ただし、原則として従業員を雇用しないことが条件となるため、加入を検討する際には業種や労働形態が適しているか確認が必要です。
特別加入の申請手続きと必要書類
特別加入を申請するためにはいくつかの手続きが必要です。まず、一人親方として所属する労働保険事務組合に申請を行います。申請時には、「特別加入申請書」や事業内容を説明する書類、また収入を証明する資料などの必要書類を提出します。また、特別加入に必要な保険料を支払うことで、加入が認められます。手続きの流れは思いのほか簡単ですが、漏れがないよう、事務組合に相談しながら進めるのがおすすめです。
特別加入による補償内容と範囲
労災特別加入制度による補償内容は非常に充実しています。
その範囲は、業務中または通勤中に発生した怪我や病気、さらには死亡事故に至る場合まで対応しています。
具体的には、医療費の補助が受けられる「療養補償給付」、仕事を休んだ際の収入減を補償する「休業補償給付」、障害が残った場合の補償を行う「障害補償給付」、死亡時の遺族への補償である「遺族補償給付」などが含まれます。
このように柔軟な対応が可能なため、特別加入は一人親方や個人事業主にとって非常に心強い救済措置として機能しています。
少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ
一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費6,000円
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
一人親方として働く際の注意点と働き方の選択肢
一人親方として成功するためのポイント
一人親方として成功するためには、しっかりとした計画と自己管理が欠かせません。
まず、自身のスキルや専門性を磨き、提供するサービスの質を高めることが重要です。
信頼を得るために、クライアントとのコミュニケーションも円滑に行い、仕事に真摯に取り組む姿勢が求められます。
また、契約書の作成や業務内容の明確化も大切です。
一人親方は請負契約が基本となるため、契約内容を事前に書面で取り交わすことで、トラブルを防ぐことが可能です。
さらに、「労災特別加入制度」に加入することで、万が一の事故に備えられる安心な働き方を確保できます。
仕事の安定を図るための施策
一人親方として仕事の安定を図るには、複数の取引先を確保することがポイントです。
一つの企業や依頼主に依存しすぎると、仕事が途絶えた場合に収入が一気に途絶えてしまうリスクがあります。
できるだけ多岐にわたるネットワークを築き、安定した受注を維持できる体制を整えましょう。
また、自己投資の一環として資格取得やセミナー受講を行い、専門性を高めることも効果的です。
これにより、受注できる業務の幅が広がり、競争力も向上します。
定期的な市場調査を行い、需要の変化に敏感に対応することも、一人親方として生き残るためのカギとなります。
事業拡大を考えた時の選択肢
一人親方が事業拡大を考えた際には、いくつかの選択肢があります。一つは、従業員を雇用して「個人事業主」として規模を拡大する方法です。
この場合、雇用管理や社会保険手続きが必要となりますが、より大きな案件を受けられる可能性が広がります。
また、法人化して会社を設立するのも一つの方法です。
法人化するメリットとして、社会的信頼度が高まり、大規模な案件を受注できる可能性が増えることが挙げられます。
一人親方と個人事業主との違いをいま一度理解し、目的や規模に応じた最適な選択をすることが重要です。
労災特別加入を活用した安全な働き方
一人親方として働く上で、労災特別加入制度を利用することは、安全を確保するために欠かせません。この制度により、万が一の労災事故が起こった際に、療養費や休業補償を受けることができます。一人親方は労働者ではないため、通常の労災保険に加入できませんが、この特別加入制度を利用することで労災のリスクに備えることが可能となります。
特別加入には、建設業や林業など特定の業種が対象となりますので、適用業種に該当するか事前に確認することが重要です。加入の際には、自治体や労災保険事務組合を通じて手続きを行い、必要書類を揃える必要があります。安全な働き方を実現するためには、こうした準備を怠らないことが大切です。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。