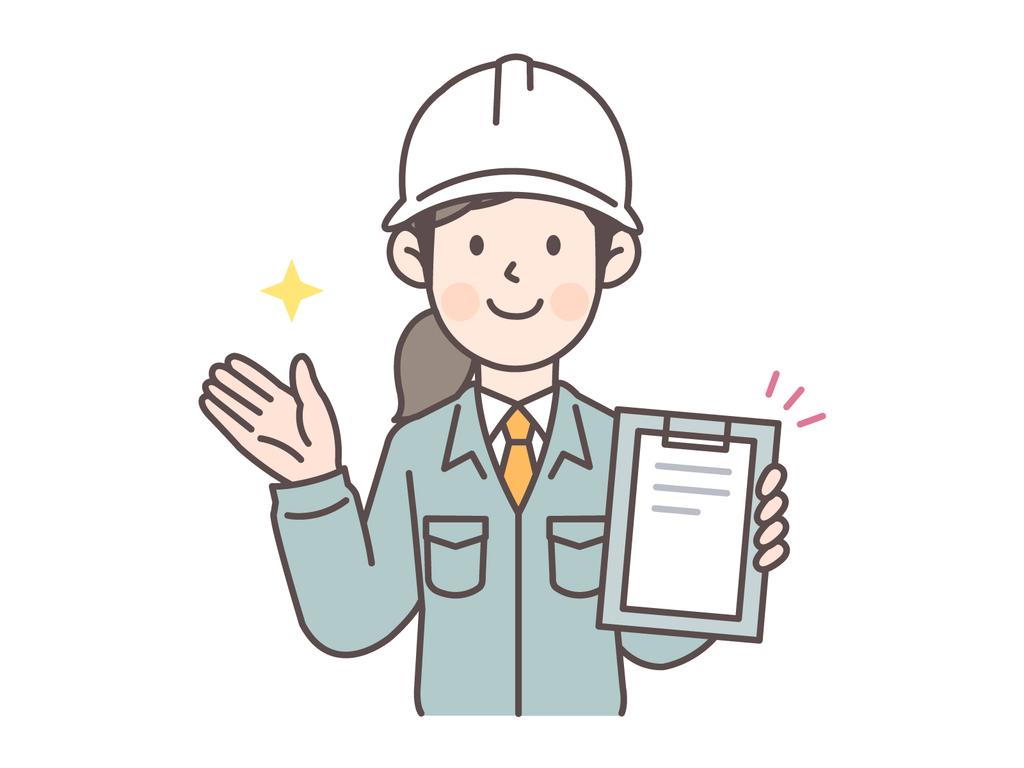一人親方 vs 個人事業主:その違いを徹底解説!あなたに合った働き方とは?
個人事業主とは法人を設立せずに事業を行う人を指すのに対して、一人親方は主に建設業や林業など、特定の業種で働く個人事業主を指します。
一方で、個人事業主は特定の業種に限定されないので、広範な分野で活動が可能です。
一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
少しでも早く・安い会費で保険加入したい一人親方の皆様へ
一人親方建設業共済会は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費6,000円
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
一人親方と個人事業主の基礎知識
一人親方とは何か?特徴と概要
一人親方とは、会社に属さず、自ら仕事を請け負って活動する個人事業主の一形態を指します。特に建設業で広く見られる働き方であり、元請け会社や他の事業者から請負契約を結んで仕事を受け、その報酬を得るのが特徴です。一人親方は、自分自身で事業の利益やコスト管理を行うため、自由な働き方が可能です。しかし、その反面、収入が安定しないリスクや社会保険の加入が任意である点がデメリットとして挙げられます。「一人親方と雇われ職人の違いとは?」という疑問については、一人親方が労働契約ではなく請負契約を基に活動する点が主な相違点です。
個人事業主とは?その定義と範囲
個人事業主とは、法人を設立せずに自らの名義で事業を行う個人のことを指します。多種多様な業界で事業を営むことが可能で、建設業に限らず小売業、サービス業、飲食業など幅広い分野で活躍しています。また、開業届を税務署に提出するだけで簡単に事業を開始できる点が特徴です。一人親方も個人事業主に分類されますが、工事や作業を請け負うことに特化しているため、全体の定義や範囲においては少し狭い要素を持つと言えます。
一人親方と個人事業主の歴史的背景
一人親方と個人事業主の概念は、日本の労働市場や法制度の中で発展してきました。特に一人親方の働き方は、建設業や運送業などの職人文化が影響しています。その歴史は江戸時代まで遡ることができ、親方が自ら職人を率いて仕事を請け負う形態が発展、現代の「一人親方」へと進化しました。一方、個人事業主は、戦後の経済成長期において企業に属さず自らの商売やサービスを展開するための柔軟な形態として認知されるようになりました。現在では、インターネットの普及により、さらに多様な業種で個人事業主として活動するケースが増えています。
建設業における一人親方の役割と位置づけ
建設業における一人親方の役割は、元請け会社やゼネコンから請け負った業務を個人または少人数で遂行することにあります。一人親方は高い技術を持つ職人が多く、作業効率や成果物のクオリティに対する責任を負っています。そのため、「事業主・一人親方」として、自らの裁量で仕事を進める自由があります。一人親方は場合によって他の労働者を年間100日以内で雇用することも認められており、短期間の人材採用によって仕事量を調整することが可能です。また、建設業のような分野では、安定した労災保険の特別加入が求められる点も特徴です。例えば、「一人親方の場合、人工出しはできますか」といった疑問に答えるときには、あくまでも請負契約に基づいた作業である点に留意する必要があります。
一人親方と個人事業主の違いを徹底比較
契約形態の違い:受注者と事業者
一人親方と個人事業主の大きな違いの一つは、契約形態です。一人親方は請負契約や業務委託契約を通じて仕事を受注し、元請け会社や顧客から直接業務を請け負う立場にあります。これにより、自身の技術やサービスに基づいて報酬を得る仕組みです。一方、個人事業主は特定の職場に縛られず、広範囲な顧客層を相手に事業展開が可能です。そのため、建設業においては「一人親方の場合、人工出しはできますか」という形で作業日ごとの単価を基準に契約が結ばれることもあります。これらの契約形態の違いが、働き方や収入形態に影響を与えている点が特徴です。
税金と社会保険の取り扱いの違い
税金や社会保険の取り扱いも両者には明確な違いがあります。一人親方は労災保険に特別加入するケースが多く、これにより「一人親方保険加入」として事故やケガへの備えが可能です。ただし、雇用保険や健康保険、厚生年金などの公的保障がなく、自身で国民年金や国民健康保険に加入しなければなりません。一方、個人事業主も同様に自ら社会保険に加入しますが、経費処理を駆使した節税が可能な分、税制面での柔軟性があります。この違いを理解し、リスク管理を適切に行うことが重要です。
収入とコストの違い:単価や経費の実態
収入やコストの面でも、一人親方と個人事業主は考え方が異なります。一人親方は「一人親方 違い 個人事業主」という視点で見た場合、建設業における日当、いわゆる常用単価が主な収入源となります。例えば職種ごとに単価が異なり、大工での例では地域によって20,000円以上の差があることもあります。一方、個人事業主は顧客ごとの取引条件に応じた報酬を得るため、収入の幅が大きい傾向があります。コスト面では、一人親方は器具や材料など必要最低限の設備だけで運営可能なことが多いものの、個人で保険料を負担するデメリットも伴います。
法律面での違い:労働法や保険の影響
法律面では、一人親方と個人事業主の取り扱いに差が生じます。一人親方の場合は、自営業者として労働基準法の直接的な適用を受けません。そのため、勤務時間や休日、残業に関する規定が存在しない代わりに、働き方の自由度があります。また、一人親方が元請け会社の指揮命令下で働く場合、いわゆる「偽装一人親方」と疑われるリスクがあり、法律違反となる可能性があります。これに対して個人事業主は、完全に独立して事業を営む立場であり、契約内容を遵守する限り自由な活動が可能です。ただし、両者共通して、労災保険や民間保険への加入が必要不可欠であり、特に建設業においては「事業主・一人親方保険加入の意義」を明確に理解し、リスクヘッジを行うべきです。
一人親方として働くメリット・デメリット
メリット:収入交渉の自由度や裁量性
一人親方として働く最大のメリットの一つは、収入交渉の自由度が高い点です。一般的な正社員の場合、給与は会社が定めた賃金体系に基づきますが、一人親方の場合、自身のスキルや経験、現場の条件に応じて常用単価を自ら設定し、報酬を交渉することが可能です。そのため、スキルに見合った報酬を得やすく、やりがいを感じられるでしょう。また、裁量性が高く、仕事の進め方や働く時間も自由に決められるため、自分のペースで働きたい方には魅力的な働き方と言えます。
メリット:仕事量や取引先を選べる柔軟性
一人親方には、取引先や仕事の内容を自由に選べるという柔軟性があります。これにより、自分の得意分野や興味のある分野で特化した仕事を受けられるだけでなく、必要に応じて取り組む仕事量を調整することも可能です。例えば、繁忙期には多くの案件を引き受けて収入を増やす一方で、休暇を取りたい時期には仕事を最小限に抑えることができます。このような働き方は、家族との時間を大切にしたい方や、趣味や学びのための時間を確保したい方にとって大きな魅力です。
デメリット:社会保障の不足や安定性のリスク
一方で、一人親方にはデメリットも存在します。その一つが、社会保障の不足です。一人親方の場合、健康保険や年金、失業保険といった社会保障制度への加入は個人で行う必要があります。加えて、建設現場での事故やケガなどに備えるためには、労災保険の特別加入が必要となるなど、自己負担となる部分が多くなります。また、仕事の受注量や景気の変動によって収入が大きく変動する可能性があるため、安定性という面では正社員と比べてリスクが高いと言えます。
デメリット:偽装一人親方問題と法律の注意点
最近問題視されているのが、偽装一人親方のケースです。これは、実際には雇用関係にあるにもかかわらず、形式上は一人親方として扱われる形態を指します。このような場合、本来であれば労働者として守られるべき労働法や社会保障が適用されず、結果として一方的に不利な条件を押し付けられるリスクがあります。一人親方として契約を交わす場合、自身の立場が適切に理解されているかどうかを十分確認し、必要に応じて法律の専門家に相談することが重要です。
個人事業主として働くメリット・デメリット
メリット:幅広い分野で活躍できる可能性
個人事業主として働く最大のメリットは、特定の分野に限らず、自身のスキルや経験を活かして幅広い業界で活躍できる可能性があることです。一人親方と個人事業主の違いとして、個人事業主は建設業だけでなく飲食業、IT業界、デザインなど多岐にわたる分野で事業を展開することができます。この自由度の高さにより、自分の得意分野で最大限のパフォーマンスを発揮でき、さらには新たなチャンスを柔軟に掴むことができます。
メリット:経費処理の柔軟性と節税効果
個人事業主は収益にかかる経費を必要に応じて計上できるため、経費処理の柔軟性があります。例えば、事業で使用する車両やパソコン、消耗品などの購入費用が経費として認められれば、課税所得を減らすことができ、結果として節税につながります。一人親方の場合も同様に経費処理が可能ですが、幅広い業界で活動できる個人事業主の方が、その選択肢が広がる可能性があります。ただし、経費計上のルールや税務関係には注意が必要です。
デメリット:責任の重さと自己管理の難しさ
個人事業主として働く上での大きなデメリットは、その責任の重さです。企業に雇用されている場合とは異なり、すべての仕事の成果やトラブルに対して自身で責任を負う必要があります。また、事業主としての意識を高く持ち、スケジュール管理や税金の適切な処理、収支管理など自己管理をきちんと行うことが求められます。一人親方を雇用する場合と同様に、事業主としての責任感が非常に重要です。
デメリット:信用確保の課題や事務作業の負担
個人事業主は法人企業と比べて信頼性が低いと見なされることが多く、信用確保が課題となる場合があります。例えば、金融機関からの融資を受ける際や、大規模な取引をする際には、充分な実績や信頼につながる書類が求められることがあります。また、事務作業の負担も増加します。確定申告の準備や請求書の発行、取引記録の管理といった雑務に時間を割く必要があるため、これが本業に支障をきたす可能性もあります。一人親方と雇われ職人の違いとは異なり、個人事業主はこうした事務負担や信用力の課題に対して特に注意が必要です。
あなたに最適な働き方を選ぶためのポイント
自身のスキルや目指す目標を明確にする
まず重要なのは、あなた自身のスキルや経験を把握し、それをもとに目指す目標やキャリアの方向性を明確にすることです。一人親方として働く場合、専門的な技術や独立心が求められるため、自分自身がそのような働き方に適しているのかをよく考えるべきです。一方、個人事業主として幅広い業務に挑戦したい場合には、事業の多角化や市場ニーズを検討することが重要です。
収入と安定性のバランスを考える
働き方を選ぶ際、収入と安定性のバランスも見逃せません。一人親方の場合、自由度が高く単価が高い傾向がありますが、収入が不安定になりやすいリスクもあります。また、保険加入の選択が任意であるため、社会保障面で不利になることがあります。一方で、個人事業主としては、事業規模を拡大したり、多様な収入源を持つことで安定性を高めることが可能です。それぞれの特徴をしっかり理解した上で、自分の生活設計に合った選択をしましょう。
就業分野や業界による選択肢の違い
就業する分野や業界の特性も、働き方を決める際に大きな影響を及ぼします。たとえば、建設業では一人親方が一般的に重要な役割を担っており、特に専門的な作業を請け負う場面が多いです。この場合、「一人親方と雇われ職人の違いとは?」という視点を見極めることで、適切な選択をしやすくなります。一方、一般的な個人事業主は、業界を問わず幅広いビジネスチャンスを見つけやすい反面、競争が激化する分野では成功するための努力が求められます。
今後のキャリアの展望を考慮する
最後に、今後のキャリア展望をしっかり見据えることも必要です。一人親方として活動する場合、スキルを磨いて常用単価を引き上げたり、信頼を得て仕事の幅を広げたりすることで成功に繋がります。また、一人親方の場合、人工出しや他の労働者の雇用が限定的であることに注意が必要です。一方で個人事業主は、将来的に法人化を検討したり、事業を拡大する道もあります。どちらの選択肢においても、自身の目標に合わせた長期的な計画が重要となります。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ
当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。
1
業界最安水準の年会費36,000円(入会金10,000円)
2
加入証明書を最短即日発行!最短でお申込みの翌日から加入できます。
3
専門の社会保険労務士が常駐。労災事故でも安心手続き!
労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。